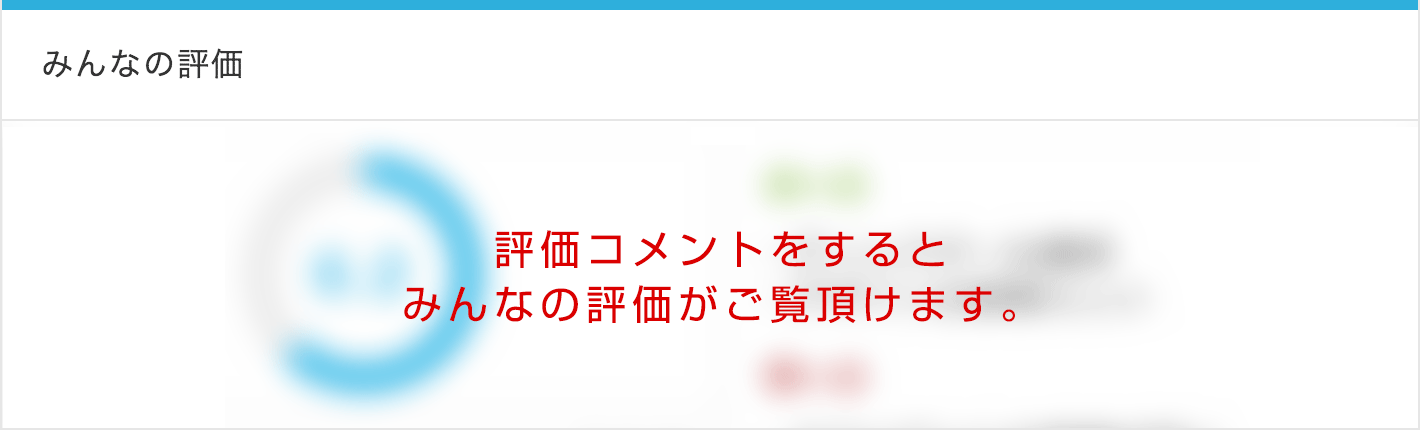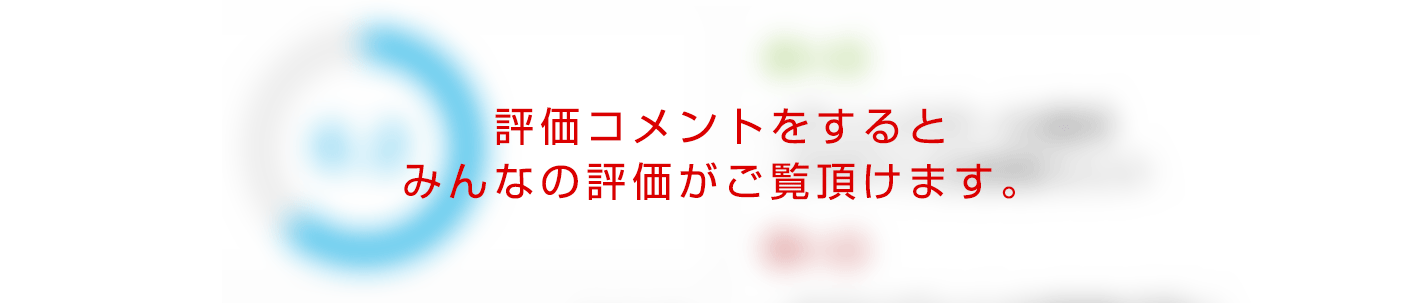オウンドメディアの大失敗
大手メーカーが陥ったオウンドメディアの大失敗

成功事例のノウハウを学んでもなかなか自社メディアに反映できない、結果につながらないと悩んでいる担当者は多い。多額の費用をかけた誰も読まないオウンドメディアの末路とは?
2016.09.25
ここ数年のコンテンツマーケティングブームにより、多くの企業がオウンドメディアを持つようになった。しかし、成功事例といえるメディアを持っている企業は決して多くない。
中には、ブランド力を活かしたコカ・コーラの「Coca-Cola Journey」や70万人以上の会員を獲得したNECの「WISDOM」、オウンドメディアをデジタルマーケティングの基軸に据えたライオンの「Lidia」のほか、大手以外でもWEBメディアに革命的な進歩をもたらした「ほぼ日刊イトイ新聞」や、月間PV数1100万、インスタグラムで国内企業アカウントでは第5位のフォロワー数を誇る「北欧、暮らしの道具店」など、注目すべき事例はある。
しかし、成功事例のノウハウを学んでもなかなか自社メディアに反映できない、結果につながらないと悩んでいる担当者は多い。 なんとなくPVは伸びているが、本当に読者に届いているのか…。代理店の設定するKPIは達成しているけれど、これは成功といえるのか…など、手応えを実感しないまま予算を費やしてはいないだろうか。
今回は大手メーカーがブランディングのために立ち上げた実際の事例をピックアップ。費用をかけているにもかかわらず、未だにファンを獲得できていない大失敗事例を紐解き、どこが悪かったのか、そして、自社が同じような運用をしていないかチェックしてみてほしい。
ブランディングのためのメディアを開設
大手製造メーカーのA社は、国内屈指の技術力を持つ企業だが、昨今では韓国や中国の廉価な製品をつくる企業の台頭により、白物やPC事業などがうまくいかず、収益の柱はtoB向けのシステムやサービスが担っていた。
そこでA社はtoB向けの製品の見込み客とのコミュニケーションや、自社のブランディングの場として、新たにオウンドメディアを開設。運用はオウンドメディアやソーシャルメディアの運用で多くの実績があるU社、制作は多くのメディアのコンテンツ制作に携わり、科学・技術系のメディアでの制作実績もあるS社に委託するなど、盤石な体制を整えた。
肝入りの編集方針
編集長はA社の広報担当者。MBAも取得している切れ者ビジネスマンだ。編成会議、レポート報告会はそれぞれ月一回。ターゲットは、次のように設定した。
- newspicksや日経新聞をよく読むリテラシーの高いビジネスパーソン。
- 情報収集はスマートフォンがメイン。アンドロイドではなく、iOSを使っている。
- よく使うSNSはFacebook、Line。
- かなりの情報を収集しており、A社の事情や技術にも詳しい。(A社社員やOBではない)
- 本メディアの「独自の情報」から、自分の仕事や生活に役立てる意欲がある。
- 情報を誰かに話す前提で記事を見ている。ソーシャル上でのシェアを積極的に行う。
- 本メディアの情報をポジティブに受け取ってくれる。
- 本メディアの情報に価値を感じ、継続して読んでくれる。
- 家族構成 妻、子供2~3人。
見識のある読者の方々からすると、すでにつっこみどころがあるかもしれないが、引き続き、編集方針や設定KPIを紹介する。
~編集方針~
- ユーザーが欲しい情報を伝えていく。
- すべての記事でA社の製品や技術、取り組みをテーマにする。
- A社の社会への貢献が伝わるコンテンツにする。
- キャッチーなタイトル、読みやすい文体。参考メディアは、newspicks、日経など。
- 記事は2000字~3000字
- 記事の更新は月4本。
~設定KPI~(2点のみ)
- 定量KPI 20000 UU(PVは追わない)
- 定性KPI A社の新しい情報を知ってもらう。
ここでも賢明な読者の方々には目をつむっていただきたい。とにかくA社のメディア運営は以上の事柄を羅針盤に進められていくことになった。しかし、その結果は散々たるものだった。
制作会社との不協和音
まずモチベーションを失ったのは、制作会社のS社の担当だった。S社では多くのヒットコンテンツを生み出しているほか、自社でも中小企業や地域のメディアを運営しており、小さなメディアでも月間300万PVを超えるメディアに成長させるなど、ある一定の効果を生み出すノウハウは持っていた。
S社はターゲットや編集方針に疑問を持ち、新たな提案を行う場面もあったが、A社としては方針を変える気はなかった。メディアの方針を決めるのには3ヶ月を要したこともあり、まずは決めた通りに、そして無難に運用をしたいという強い意向があった。
またユーザーインタビューの仕方にも入れ違いがあった。S社では実際の読者へ声を聞かなければ意味がないとしたが、予算の都合もありU社の社員でターゲットに合いそうな人物を毎月2人呼んだ。その場で感想を聞き、10段階評価をしてもらった。毎月違った2人が呼ばれるため、継続性がないほか、個々人で好みが分かれるため修正の方向性も毎月ぶれた。
当然A社とS社の間では原稿の修正も多く発生した。S社ではA社の製品をテーマにしつつ、外部の専門家への取材や、A社技術だけでなく業界全体の最先端技術も取り扱うなど、制限の中でユーザーにとって有益となるような企画・制作を行ったが、A社からすると自社のアピールが少なく無意味なコンテンツに映った。自社のPRが最優先であるため、A社と関係のない情報はいらず、A社の高い技術力を詳しく説明することや、A社がいかに社会に貢献しているかを伝えなければ意味がないと考えた。S社の担当とA社の担当は、互いによい感情を抱かなかった。
ユーザー不在のメディアへ
結果、FIXを優先し、S社ではA社の意向を優先させるようになる。間に入るU社もA社の方針に疑問を抱きつつも、強くは提案を行わなかった。ただでさえFIXがギリギリなことが多かったため、局面を荒立てたくなかった。またA社は現状以上の予算を出さないと決めていたこともあり、不評だったデザインやシステムの改修なども積極的には提案しなかった。
U社S社が積極的な提案を行わないため、A社はよりリーダーシップを発揮していく。取り上げるテーマ(製品)も全てA社が決め、技術の特徴や説明、優位点を多く入れるようにと原稿毎に要望を出した。
その背景には、広報と事業部との関係性があった。原稿の事業部確認をスムーズにいかせるため、現場の技術者や事業部の担当者の意見がフィードバックに強く反映された。現場は技術に特別な思い入れをもっており、あれもこれもと要素が増えた。これにより、初期の公開記事にこそ、難しい技術をわかりやすく説明した興味深い記事もあったものの、徐々にPR色が色濃くなり、できあがったのはプレスリリースを長く、詳しくしたような単調な記事が集まるメディアとなった。
コストに見合わない実績
~公開から1年でのA社オウンドメディアの実績~ ・月間最高PV 約10000 ・月間最高UU 約1000 ・1記事あたりの最高PV 約3800 ・月間運用コスト 100万~200万円アクセス解析を行うと、読者のほとんどが本社PCからのアクセス。またオーガニックな流入はごくわずかで、SNSからの流入とダイレクトが大半を占めた。ここで技術の深掘りや、事業部の意向を尊重するなら、社員・OB向けのメディアにしてはと提案もあったが、A社編集長はそれを拒否。本施策はあくまで外部向けへのブランディングでなければ意味がなく、そこは変えられない。UUが伸びないのは、コンテンツ及び制作者が悪いとの考えから、制作会社を変更。よりキャッチーなコンテンツを得意とする有能なベテラン編集者がいる会社を選んだ。
そして月日が流れた――。記事はキャッチーになったし、文字数も短くした。当然、記事の数も増えている。しかし、それでも依然として20000PVにも達することはない。UUも伸び悩んでいる。
A社のオウンドメディアは、いまだに熱心なファンを獲得できないまま、今も運用が続いている。